2024年7月3日より新紙幣の発行が開始されます!
新紙幣発行の本当の理由は、高齢者などが中心に行っていると言われる「タンス預金」のあぶり出しが目的ではないかと噂されています。
タンス預金あぶり出しが目的であれば、「手元にある紙幣は2024年どうなるの?」心配になります。
この記事では、
- 新紙幣はタンス預金あぶり出し?
- 2024年旧札は使えなくなる?
新紙幣はタンス預金あぶり出しなのか、2024年旧札は使えなくなるのかについてご紹介していきます。
新紙幣の発行がタンス預金あぶり出しだという噂は本当なのか、2024年に旧札は使えなくなるのかについてご紹介していきます。
記事最後の「まとめ」にこの記事の内容を簡潔にまとめています。
お急ぎの方は「目次」より「まとめ」に飛んで記事の内容をご確認くださいね♪
新紙幣はタンス預金あぶり出し?
定期的な紙幣の改新や偽装防止は表向きの理由で、「タンス預金」あぶり出しが真の目的ではと噂されています。
SNSでも新紙幣変更について様々な憶測が流れていました。
Richee Hauser@richeehauser Xより引用新一万円札かぁ!タンス預金のあぶり出し?2024年度から。
— Richee Hauser (@richeehauser) September 1, 2021
小猿さん@RightOnly Xより引用偽造防止とタンス預金あぶり出して納税増額
— 小猿さん (@RightOnly) April 9, 2019
「タンス預金のあぶり出し」とは、どういうことなのでしょうか?
下記の2つがその方法ではないかと言われています。
- 旧紙幣の廃止
- 預金封鎖
タンス預金をあぶり出す方法として2つの方法が考えられると言われています。
ひとつづつ詳しく見ていきましょう!
旧紙幣の廃止
旧紙幣を廃止することは、上記が目的ではないかと思われます。
旧紙幣を廃止することになれば、「タンス預金」を新札に交換しなければただの紙切れになってしまいます。
旧札が無効になれば「タンス預金」を銀行に持ち込み、新札へ両替を行います。
新札に交換してまた「タンス預金」しちゃえばいいんじゃないの?と思いますが、両替するときに「両替依頼書」を記入します。
このとき住所や氏名も記入しなければいけません。
ということは、誰が両替したのか、両替の金額など履歴が残ってしまいます。
意図的にタンス預金していたとなれば、脱税や違法取引などの不正蓄財などの疑いがかかってしまう恐れも。
そうなるのであれば、多くの人が消費や投資をしようと考えます。

すわなち旧紙幣の廃止の狙いは、「タンス預金」の消費や投資への促進し、市中にタンス預金を流通させることで経済に貢献させることが目的となります。
経済に貢献する効果はありますが、金融機関や日本銀行にとっては業務の負担は大きくなるのがデメリットになりますね。
預金封鎖
「タンス預金」のあぶり出しの方法として、「預金封鎖」があります。
預金封鎖とは、
- 預金の引き出しができなくなる
もしくは - 預金引き出しの金額を制限する
ことです。
「タンス預金」と「預金封鎖」はどういう関係があるの?と思いますが、
預金封鎖の場合は、旧紙幣の廃止もセットで行われる前提での「タンス預金のあぶり出し」になりますが…
終戦後、1946年に日本でも「預金封鎖」が行われたことがあります。
このときも新紙幣が発行されています。
新紙幣の発行により、旧紙幣が使えなくなるので国民は「タンス預金」を銀行に預金をしました。
政府は、国民が預金をしてすぐに「預金封鎖」を実行しています。
このときの「預金封鎖」の目的は、
- ハイパーインフレの抑制
- 政府財政の立て直し
でした。
「預金封鎖」により最大90%の財産税を徴収し、その後「預金封鎖」を解除しています。
2020年時点の日本の借金はGDPの2倍を超えていて、戦後と似た状況と言われています。
1946年と同様の「預金封鎖」は起きないとは言えませんが、現状新紙幣による「預金封鎖」は考えにくいのではないかと思われます。
2024年に「預金封鎖」が行われれば大きな混乱がおきることも想像がつきます。
「預金封鎖」は考えにくいと思いますね!
2024年旧札は使えなくなる?
- 2024年新札が発行されても旧札は使える
2024年上期(4~9月)新紙幣が発行されることが発表されています。
実際に新紙幣が発行された場合、旧札はどうなるのか?と疑問に思いますが、現在発行されていない旧紙幣・旧硬貨26種類も現在使用できるようになっています。
明治18年発行の旧壱円札が現在でも使用できちゃうのが驚きです!
https://twitter.com/ncb_since1989/status/1452280341268361216より引用そうなんです。なんと今でも明治18年発行の旧壱円券も使えてしまいます。
— NCB Lab. | FinTech解説 (@ncb_since1989) October 24, 2021
日本銀行法第46条第2項の「法貨の強制通用力」では、銀行券(紙幣)は一度の支払いで無制限に使えると定められています(貨幣は上限20枚)。
つまり、旧壱円券1万枚で1万円の支払いをされてもお店は拒否できないのです… https://t.co/kdoYMSPmj9 pic.twitter.com/cxEd6zcSEq
しかも旧紙幣・旧硬貨の使用期限は設けられていません。
ということは、今回2024年に新紙幣が発行されても旧札は使えるということになりますね!
▼ 新札が発行されたら旧札を両替した方がいい?気になる方は下記をCHECK!
あわせて読みたい ✓ 新札になれば旧札はどうなる?旧札を新札にする方法や手数料も!
まとめ
新紙幣はタンス預金あぶり出し2024年旧札は使えなくなる?ついてご紹介しました。
新紙幣はタンス預金あぶり出し?
2024年新紙幣が発行されても旧札の使用はできます!
新紙幣発行による「タンス預金」のあぶり出しは考えづらいとは思いますが、常に情報を収集し、リスクも理解した上で「タンス預金」の在り方を検討することも必要かもしれませんね。

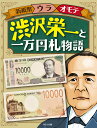



コメント